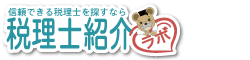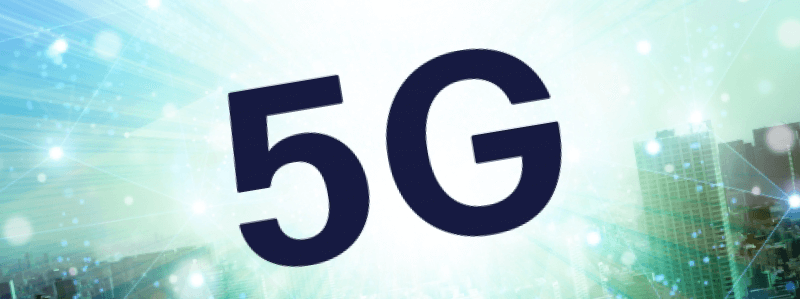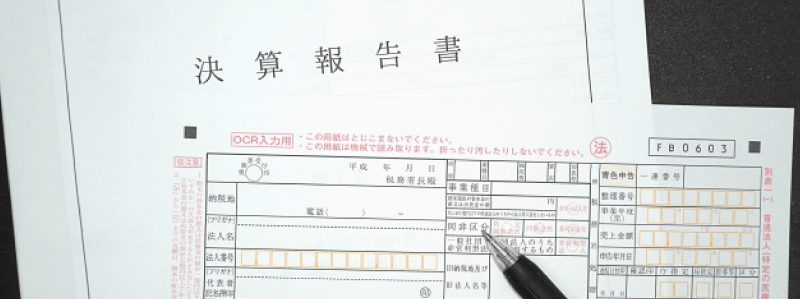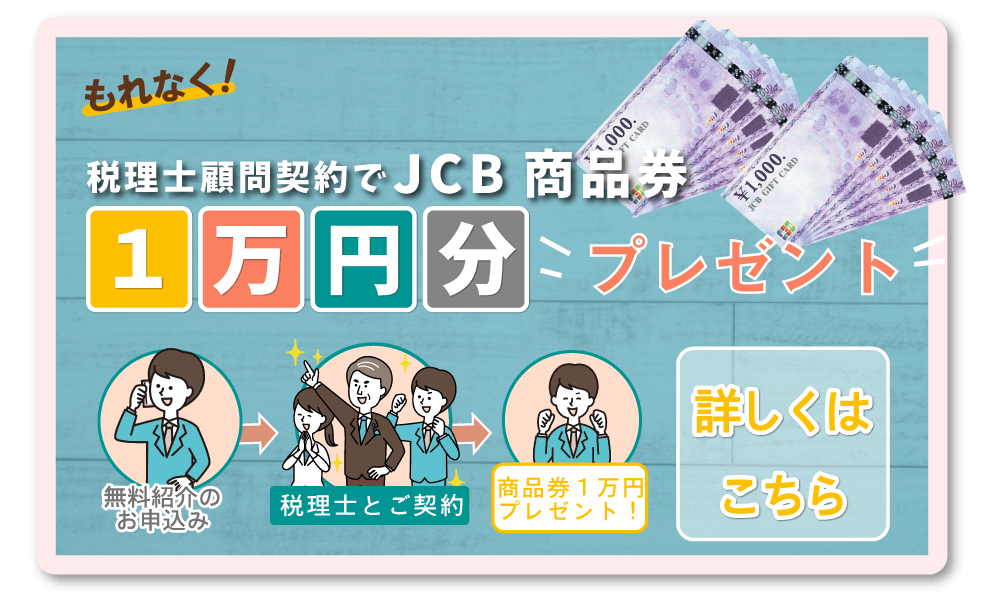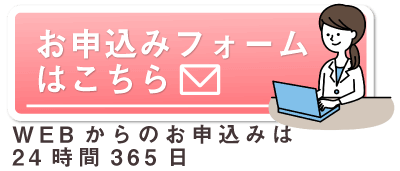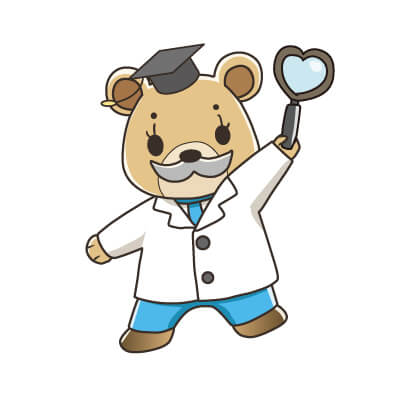目次
今回は、法人化メリットの中の「保障」と「事業承継」、そして「消費税」に関して見ていこう。法人化することで、経営者のみならず、配偶者や家族従業員並びにその他の従業員は、健康保険や厚生年金という手厚い保障を手に入れることができる。また、個人事業主の悩みの種ともなっている「事業承継」や「相続問題」についても一定の方向性が見えてくるはずじゃ。
1、健康保険の場合
個人事業の場合の健康保険に関しては、基本的には国民健康保険となるが、たとえ社会保険に任意で加入したとしても、加入できるのは従業員に限られるため、個人事業主の保障は国民健康保険ということになる。これが、法人化となると、たとえ経営者一人であっても社会保険に強制加入となるのじゃ。
医療費の負担や入院などにおける高額療養費や出産育児一時金については国民健康保険も健康保険組合等の社会保険も同様の給付を受けられるが、社会保険に加入すると、国民健康保険よりさらに保険給付のメニューが増えるのじゃ。病気やケガ・出産などで仕事ができなくなり収入が減少したときに、所定の保険給付を受けることができるのじゃ。
病気・ケガの場合は、傷病手当金を1年6カ月、出産の場合は、産前42日間、産後56日間のうち仕事をしなかった日につき標準報酬日額の3分の2が支給されるのじゃ。またこれに加え、産前産後の休業期間及び3歳に達する子を養育するための育児休業期間については社会保険料が免除されるのじゃ。
2、厚生年金の場合
公的年金についても社会保険と同様に、個人事業の場合には国民年金への加入となるが、法人化して厚生年金に加入することができると、保険料は高くなるものの、将来受給できる年金額は大幅に増えることになる。もらえる年金が国民年金の場合、満額受給できる人でも約78万円程度であり、老後資金としては心細い金額と言わざるを得ない。
厚生年金に加入すると、老齢基礎年金(国民年金部分)に、支払った保険料に応じて支払われる老齢厚生年金が上乗せされるため、老後資金を増やすことができるのじゃ。この厚生年金保険料と健康保険料は、一般的には法人と個人の折半で負担することになり、法人にとっては法定福利費という損金に算入され、個人にとっては社会保険料控除として、ともに課税所得を減らす効果もあるのじゃ。
3、事業承継に係るメリット
近年、よく耳にするのが「事業承継」の問題じゃ。個人事業の場合、事業主が死亡して相続が開始されると、遺産分割協議が終了するまでの間個人名義の預金口座が凍結されるため、仕入れ等の支払に支障を来し、事業の存続が危ぶまれる状況に陥るケースも多いのじゃ。
相続人が複数(多数)存在するときは、事業用の資産がすべて後継者に相続されるとは限らず、場合によっては、事業資産が複数の相続人に分散相続されて事業の継続を担保できない状況に陥ることもあるのじゃ。個人の相続に関してはもう一つ問題があり、事業用資産、中でも土地を中心とした不動産は価値が高いことがほとんどであり、多額の相続税負担が生じる可能性が高いのじゃ。
一方、法人化すると、経営者(代表者)の死亡によって会社の預金口座が凍結されるようなことはなく、会社の資産が経営者の相続問題の対象となることはないため、会社の運営に支障が出ることはないのじゃ。事業承継と点では、法人化すると次のようなメリットがある。
(表1)法人化による事業承継時のメリット
| メリット項目 | 説明 |
|---|---|
| 円滑な経営者交代 | 個人事業主との最も大きな違いは、法人化によって全く別の人格を作り出せると言う点にある。法人は個人たる経営者とは別人格であるため、経営者が死亡したとしても、組織の後継者によって事業は継続され、会社は存続される。この後継者は創業家の人間に限る必要はないため、内部人材から登用するか、場合によっては外部から優秀な人材を招くことも可能なわけじゃ。会社は、事業の継続性担保が第一なのじゃ。 |
| 代表の相続問題排除 | 経営者の死亡によって生じる相続問題は、基本的には法人には関りがない。死亡した経営者が所持していた株式を相続するのみじゃ。 |
| 相続税対策 | 法人化した場合、事業自体は法人の株式を移転することによって承継されることになる。経営者自身が持つ株式は、生前に後継者に対して少しずつ移転しておくことで、少なからず相続税対策を講じることにつながるのじゃ。 |
| 事業売却が容易 | 法人化した場合、事業自体は法人の株式を移転することによって承継されることになる。経営者自身が持つ株式は、生前に後継者に対して少しずつ移転しておくことで、少なからず相続税対策を講じることにつながるのじゃ。 |
4、消費税の取扱い
消費税については、会社設立によって、一時的ではあるが免税事業者となることで、面倒な税管理と申告・納税事務を省くことができる。消費税の納税は、売上に係る消費税額(これを仮受消費税という。)から仕入れに係る消費税額(これを仮払消費税という。)を控除した額となり、会社が申告・納税者として消費税を納める義務を負うが、基準期間(注1)における消費税の課税対象売上高が1,000万円以下の事業者や、特定期間(注2)における課税売上高が1,000万円未満であるなど、一定の要件を満たす場合は、免税事業者(消費税の申告・納税義務を免れる)となれるのじゃ。
(注1)基準期間
消費税の課税年度の前々期を基準期間といい、この2年間の課税売上高が1,000万円を超えていると消費税の課税事業者となる。新設法人の場合は、この前々期がないため基準期間がないことになり、免税事業者となる。
(注2)特定期間
消費税の課税年度の前期(前年度)の上半期を特定期間といい、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その期より消費税の課税事業者となる。
この制度により、創業から2年間は基準期間における課税売上高がないため、原則として申告・納税が免除されるのじゃ。したがって、個人で創業し、2年後に一旦廃業して法人を設立すれば、最長で4年間は消費税の免税事業者となることができることになる。また、個人事業で消費税の課税事業者となる程度の売上げに達したときに法人化すると、この2年間の免税期間は、税務面では非常に有益な期間になるということがわかると思う。
しかし、これには制約もある。資本金が1,000万円以上の会社や、資本金が1,000万円未満であっても、その会社の株式の50%超を保有する一定の支配株主が存在する「特定新規設立法人」については、基準期間のない第1期、第2期についても消費税の申告・納税義務があるのじゃ。
5、まとめ
前回解説した所得税と法人税の関係や今回の解説で、個人事業主から法人化するメリットの概要が見えてきたのではないかな? 今は意識することがないかもしれない「事業承継」の問題にしても、事前に知っておくことは必要じゃ。
近年は、せっかく創業して事業が軌道に乗ったとしても、後継者がいないばかりに止む無く廃業というケースも目立つ。個人事業者でもイノベーションに近い技術を持つ町工場も数多くあるため、技術を含めた事業の売却もまたこれからの大きな課題となっていくのではないだろうか。
このあたりのことも含め、顧問税理士を置いて、将来の事業の在り方を想定しておくことも創業者としての重要な役割じゃ。まだ顧問税理士がいないようなら、税理士紹介会社へ相談するとよい。該当業種に詳しい有能な税理士を紹介してくれるはずじゃ。