税務調査を意識した会計処理と税理士との付きあい方《役員退職慰労金》
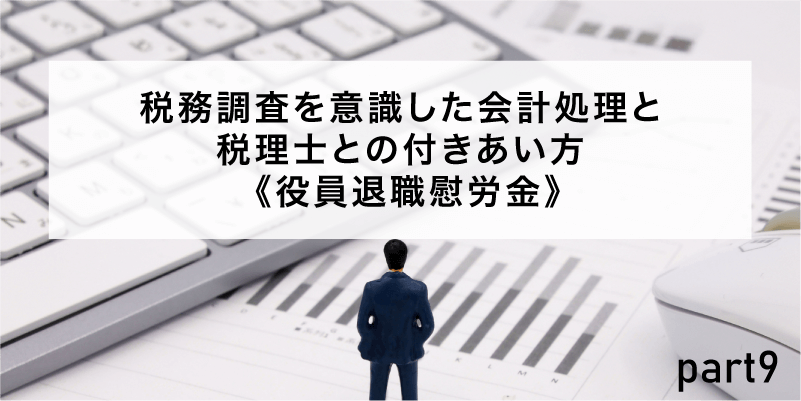
役員に支給する金銭の中で最も金額が大きい「役員退職慰労金」について解説します。役員退職慰労金は、金額が大きいこともあって税務調査では見られやすい項目の一つです。会計処理と税制対応上の手続き面でポイントとなるのは、「支給日と損金算入時期のタイミング」「支給額の適正性」の2つです。
手続きの適正性
今回のテーマである「役員退職慰労金」や、part8の「役員給与」の支給に関しては、本来は規程が設けられ、その規程に基づいて支給されるのが基本です。ここで言う規程とは、「役員退職慰労金規程」「役員報酬(給与)・役員賞与規程」という名称で、支給金額算定根拠や時期、その他支給に係る事項を定めているものです。年度ごとの役員給与の総額は株主総会で決議し、各役員の支給額は取締役会なり監査役会で各々決定するという流れになりますが、役付け役員に対する支給額の根拠や、時期などについては規程で決まっているケースが多いです。
役員退職慰労金も、規程で計算根拠を定め総額を株主総会に付議するのが一般的ですが、中小企業では規程の整備が進んでおらず、オーナー社長のもとで比較的自由に決められることが多いようです。また、大企業では規程廃止の傾向が強まっていることもあり、今回の解説では、規程の有無に直接触れずに税務調査の視点のみで話しを進めることにします。
損金算入の要件を具備する手続きか
役員退職慰労金の支給にあたっては、その支給額が株主総会の決議によって確定した日の属する事業年度の損金に算入されるのが原則です。しかし、「退職する各役員の慰労金については取締役会に一任する」旨の決議をした場合には、取締役会において具体的に支給額が確定した日の属する事業年度の損金となります。税務調査は、この本則にしたがって株主総会及び取締役会議事録の閲覧を通して手続きの適正性を確認することからはじまります。そして、退職慰労金の支給日と損金算入の時期は次のように整理することができます。
【退職慰労金の支給日と損金算入時期】
| 会社の手続き | 退職年度 | 株主総会の決議年度 | その後の事業年度 |
|---|---|---|---|
| (1)退職慰労金支給 | 損金算入可 | 損金算入可 | 損金算入可 |
| (2)仮払金として支給 | 損金算入不可 | 損金算入不可 | 損金算入不可 |
| (3)未払金として計上 | 損金算入不可 | 損金算入不可 | 損金算入不可 |
(1)の場合は、どのタイミングでも会社の支払債務が確定していれば、いずれも損金算入できます。しかし、会計上「その後の事業年度」に支給する場合は、支払債務が確定した事業年度末に未払金に計上しなければなりません(当該事業年度の損益を確定させるため)。
(2)は、仮払金処理自体が会計の適正性の問題となりますが、税務上も会社の支払債務が確定したとは言えないため損金算入は不可。損金算入が可能となるのは、全ての要件を満たす「株主総会の決議年度」において、「退職慰労金」として処理する場合のみです(これは、退職年度に仮払金で処理していたものを、株主総会決議後に退職慰労金として処理することを含む)。
(3)期末における会計上の処理は、「未払金」という負債勘定と「退職慰労金」という費用勘定を立てて処理し、当該年度の費用を確定させるため正常な処理です。一方、税務上はこの年度は損金の額に算入されないため、課税所得に加算されることになります。しかし、次年度に入り株主総会で債務が確定した日の属する事業年度の法人税申告書において、税務調整して損金算入が可能となります。このように税務上は、あくまでも会社の支払債務が確定しないと損金に算入できないということに注意が必要です。
勤続期間による取扱いの違い
退職所得は、下記の計算式で算出されます。退職所得控除額の計算方法は下記のとおりですが、かつての天下り問題などへの批判から、2012年度の税制改正以降、勤続年数が5年以下の役員(これを特定役員という)の退職所得の計算にあっては、2分の1規定が廃止となっています。
〔(収入金額)-(退職所得控除額)〕×1/2
【退職所得控除額の計算方法】
| 勤続年数 | 控除額の計算方法 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円+(70万円×(勤続年数-20年)) |
《計算例》
退職金:2,400万円、勤続年数:36年の場合
退職控除額=(800万円+(70万円×36年-20年)=1,920万円
2,400万円-1,920万円×1/2=課税所得240万円
240万円に対する所得税率及び復興特別所得税率(2.1%)を乗じた額が退職所得税額となる。
所得税額は、240万円×10%-97,500円(課税所得控除)=142,500円+2,990円
支給額の適正性をチェック
損金算入のタイミングとともに注目されるのが支給額です。お手盛りで不当に高額な支給額となっていないかをチェックされます。不相当に高額であるとされた場合は、その不相当部分が損金算入できなくなります。ここで問題となるのが「相当額」じゃが、税務署はいくつかの判断基準をもっています。税務署には、全国の業界と規模別の役員報酬や退職慰労金のデータが整備されているので、まずはこのデータとの照合が行われることになります。
一般的に、「退職慰労金支給規程」を整備する企業では、役員の職制や在任期間に応じて「功績倍率」というものを定めています。この倍率は企業によって異なるが、役員の最終月額報酬のおおよそ1倍~3倍で設定されていると言われています。この倍率設定においても「社会通念」や「公正妥当性」を勘案しなければならないので、決定に際して使用した資料や関係会議の議事録等は確実に残しておくことが必要といえるでしょう。
金銭以外の給付にも注意
稀に、現金以外に会社所有の不動産などの現物を支給する場合もあります。このような場合は、客観的に評価できる資料を整備しておくことが必要です。不動産なら、不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」、絵画なども一般に公表されている市場評価額を把握しておくことが必要です。金銭に加えて支給するような場合、金額の相当性判断の材料にもなるので、給付前の資産価値評価は必須です。
特殊な場合
役員退職慰労金は退職時に支給されるもので、それ以外に支給されることは考えられませんが、税務上は例外として以下のケースを挙げ、退職給与として損金算入を認めています。
(1)常勤の役員が非常勤役員となった
(2)取締役が監査役になった
(3)役職や職務の内容が変更となり、変更後の報酬が著しく減少した(概ね50%以上の減少)。
なお、これらのケースは実態としてその状態になっていることが必須要件であるため、税務調査の際は会社の決裁プロセスの確認、会社内外の関係者への聞き取り等を通して実態との整合性を入念にチェックされることになります。問題となるのは、創業者が一線を引いたとして、職制上(形式)は相談役などに就任して機関決定のプロセスから離れたとしても、実際の決裁過程において意思決定に加わっているようなケースです。
税務調査において指摘された場合、当人に対して支払った退職慰労金は、税務上は「賞与」として扱われて損金不算入となり、加えて、給与所得の源泉徴収漏れによる追加納付と延滞税が発生することになるため、まさに「踏んだり蹴ったり」の目に遭うことになります。
一方、受け取った側も退職所得ではなく給与所得として扱われるため、退職給与の計算のような特別の控除額や2分の1を乗じるような特例はなく、しかも他の所得と合算して計算することになるため、金額によっては高税率の所得税が課させることになります。会社・役員ともに痛い思いをしなくてすむよう、このようなケースでは、事前に税理士に相談して税務上のリスクを排除しておくことが必要になります。
まとめ
今回の退職慰労金を含め、役員報酬に関わるものは基本的に損金不算入であり、然るべき要件を備えた時にはじめて損金算入が認められるという認識でいたほうが間違いありません。このような視点をもって税務調査を念頭に置けば、日常的な経理処理において絶えず税制面での要件を満たすことに注意を払う必要があるということに加え、客観的な検証手段の確保という意味においても、税理士の活用が望まれるところです。

今井 俊樹
ユーザーが本当に良い選択ができるマッチングサービスを作りたいという思いから、「税理士紹介ラボ」の立ち上げを起案。企業間のアライアンス事業や、WEBサービスの企画・運営を手掛けた経験を基に、依頼者と税理士がwinwinの関係になれるサービスを提供。500名以上の税理士と面談を行い、毎年3000件以上のマッチングを成功させている。
ご利用無料 24時間受付 最短即日返信
無料で税理士を紹介してもらう

