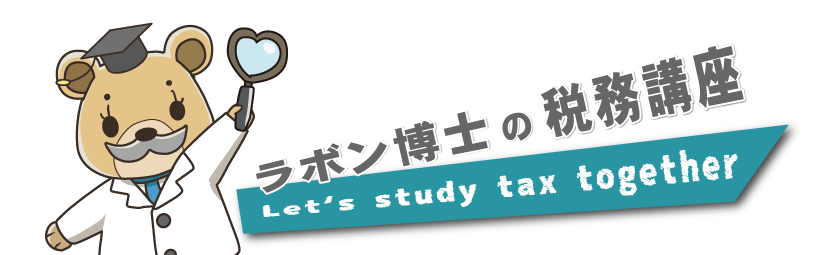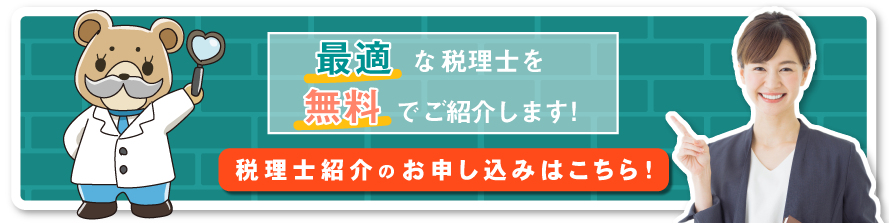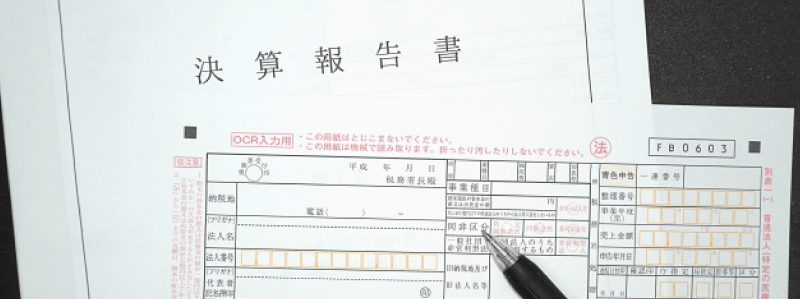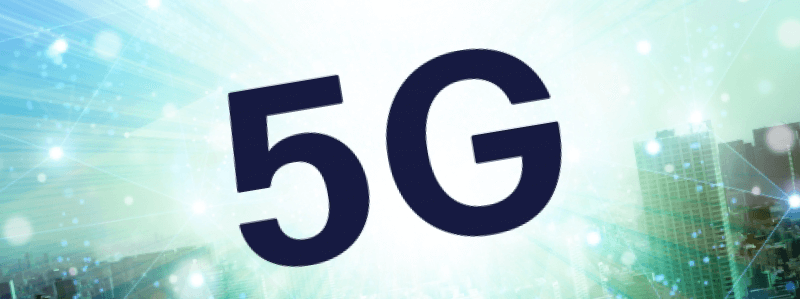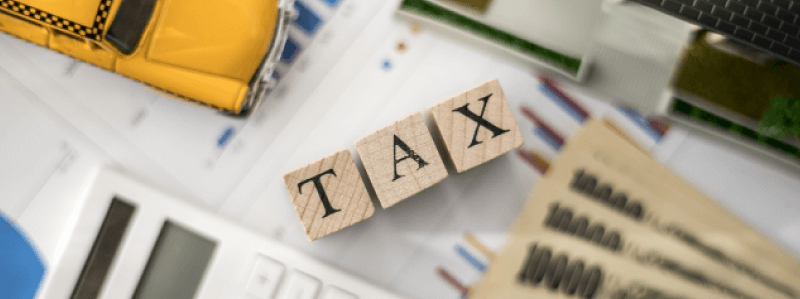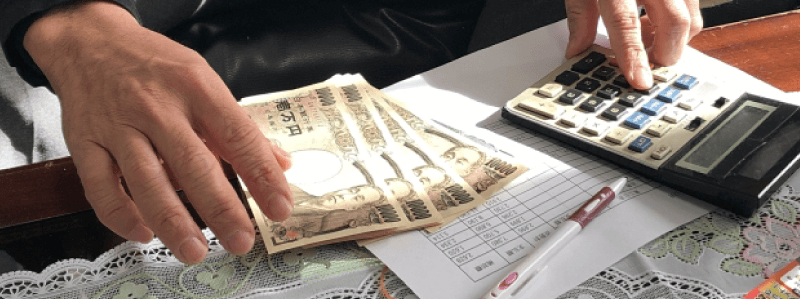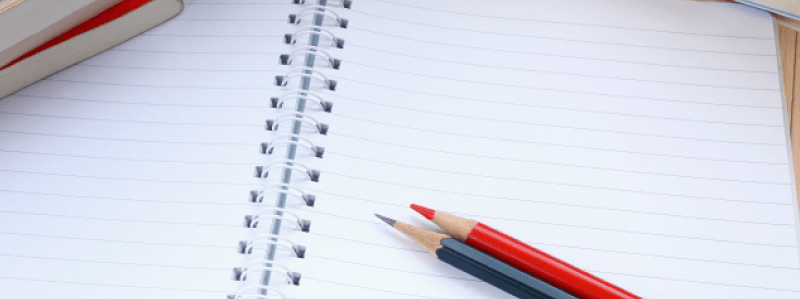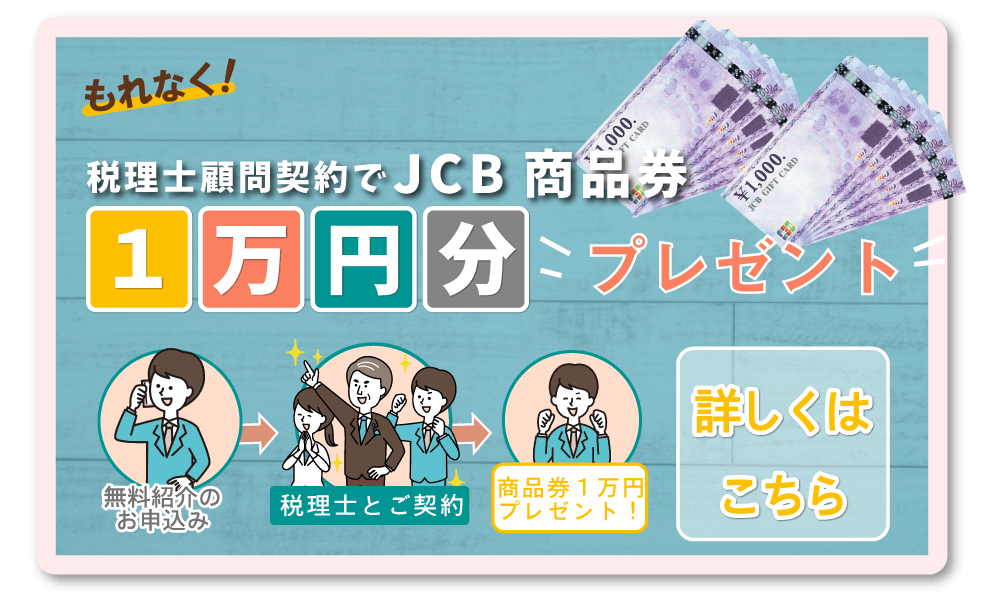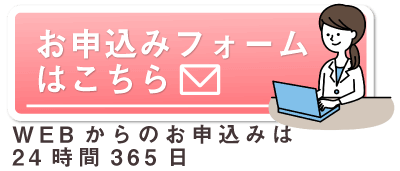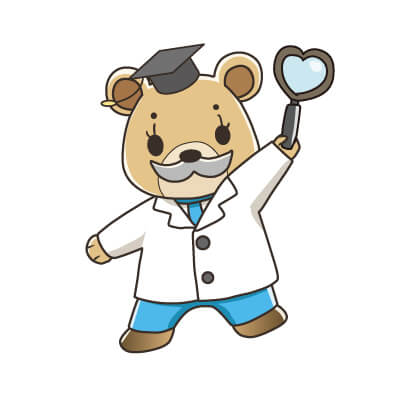目次
今回は、税理士と会計士の違いについて解説しよう。税理士と会計士を混同している会話をよく耳にするが、これは、この二つの職業とそれを裏付ける国家資格への認識不足からくるものじゃ。
ちなみに、会計士は正式名称を「公認会計士」という。以下、それぞれの職務と資格試験を対比して違いを見てみよう。
1、税理士と公認会計士の職務比較
| 税理士 | 公認会計士 | |
|---|---|---|
| 法令 | 税理士法 | 公認会計士法 |
| 使命 | 税理士は、税務の専門家として、申告納税制度の理念に従い、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図る。 | 監査及び会計の専門家として、投資家や債権者の保護を図って、国民経済の健全な発展に寄与する。 |
| 本来業務 | 他人の求めによって、「税務代理」、「税務書類作成」、「税務相談」に応じる。代表的業務は、「確定申告書等税務書類の作成」、「税務調査対応」など。税務は税理士の独占業務。 | 企業、公益法人など幅広い対象について、独立の立場で監査意見を表明し、法人の財務諸表の信頼性を担保する。「監査」業務は公認会計士の独占業務。また、監査には、金商法や会社法等に基づく法定監査と法定監査以外の監査がある。 |
| 付随業務 | 財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務(コンサルタント業務など)。 | 「会計」、「税務」、「コンサルティング」など。なお、公認会計士は税理士登録することにより税務に関する業務を行うことができる。 |
2、資格試験と登録要件の比較
| 税理士 | 公認会計士 |
|---|---|
《会計学》
《税法》
|
《短答式》・・・4科目必須
《論文式》・・・4科目必須、選択1科目
(経営学、経済学、民法、統計学)から1科目選択で、9科目合格が必要。 |
《試験の特徴》
【2018年合格率-総合】全科目:12.8% |
《試験の特徴》短答式試験の合格者が論文式試験に進む(短答式試験免除制度あり)。
【2018年合格率-総合】短答式:25.3%、論文式:11.1% |
| 税理士登録には、「試験合格の前後通算で2年の実務経験が必要」 | 公認会計士登録には、試験の前後通算2年の実務経験と「論文試験合格後、3年間の実務補修が必要」 |
このように、両者には、試験科目、選択科目の扱いなど、相違点が多いのじゃ。公認会計士は、日本国家三大資格と言われるだけあって、試験の科目数、科目合格の有効期限、試験以外の要件具備とどれをとっても大変じゃ。
3、実務対応は?
職務内容と資格試験の比較で両者の違いはつかめたと思う。税務」と「付随業務」で競業するためか、この二つは混同されやすいのじゃな。「独占業務」という観点ではどうじゃ?「監査」は公認会計士の独占業務じゃが、「税務」は微妙じゃ。法律上は税理士の独占業務じゃが、公認会計士は、税理士に登録さえすれば「税務」を扱うことができるからじゃ。
こうやって比較すると、税理士が見劣りするかもしれないが、これは見方によるな。なぜなら、税務に関して言えば、試験科目を比較するとわかるように、公認会計士の受験必須の税務科目は1科目(租税法)しかない。登録すればできるとは言っても、本当に税務がわかるのか? 制度上可能であることと、実際に「できる」こととは別物じゃ。会計と税務の専門家を選ぶとすれば、これら先生方の実務上の得手・不得手も含め、入念な検討が必要じゃな。