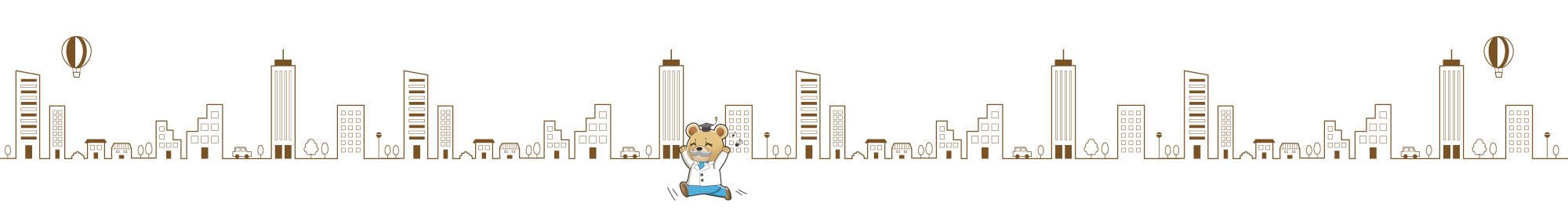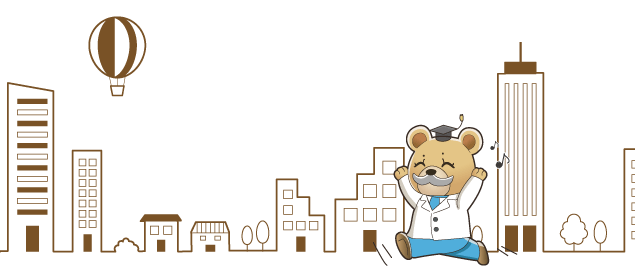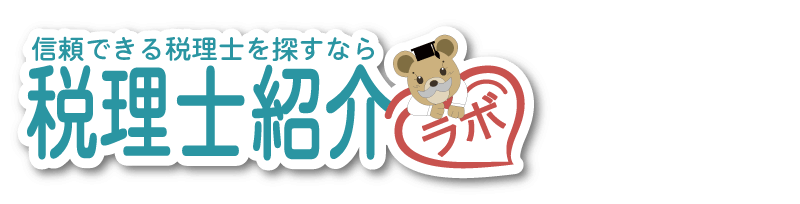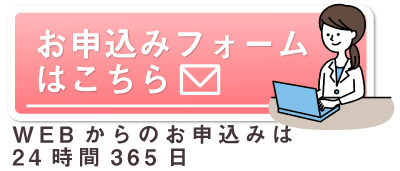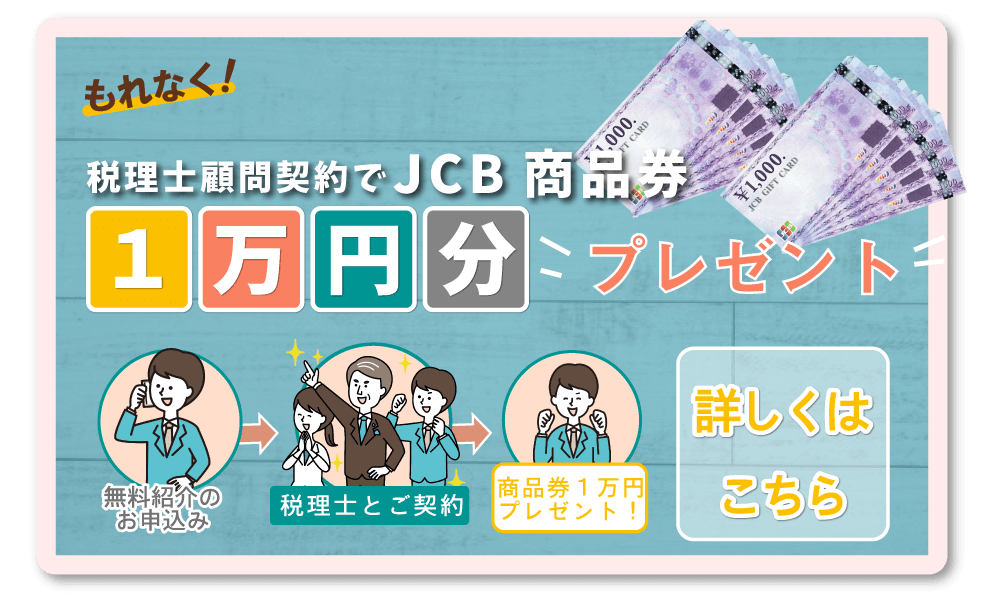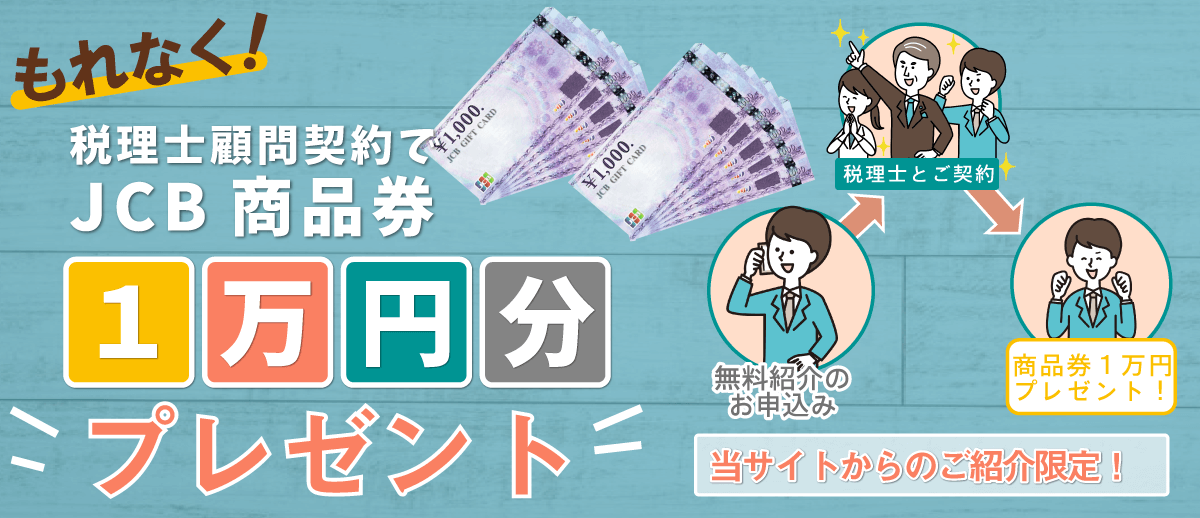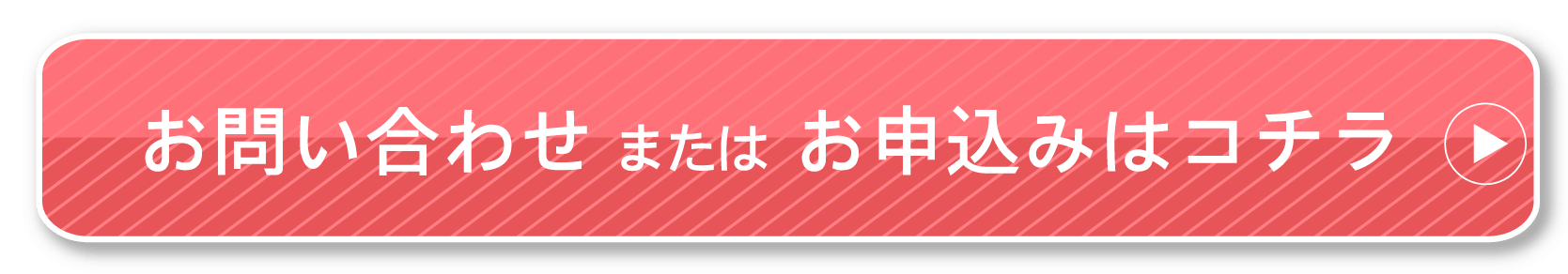用語集Glossary
き
◆ギアリング比率
ギアリング比率とは、有利子負債/総資産×100という計算で算出され、数値が小さいほど企業の財務状態が安定していると判断されます。負債比率、レバレッジ比率とも呼ばれることもある。
◆企業価値
企業価値は、しばしば株式時価総額で語られることがありますが、本質的にはゴーイングコンサーン(将来にわたって事業を継続するという前提)のもと、その企業が将来にわたって生み出す利益の合計額と定義することができます。したがって、株式時価総額のみならず、資金調達に係る負債総額の時価をも含めたものとする概念と言えます。
◆基礎控除
基礎控除とは、所得税額の計算をする場合に、納税者全てに一律の金額を所得金額から控除できることをいいます。人的控除の一つで、全ての納税者に無条件に適用されます。所得税が38万円、住民税33万円。
◆寄付金控除
寄付金控除とは、地方公共団体や認定NPO法人など、特定の団体に寄付や政治献金があるときに受けられる所得控除です。寄付した金額について所得控除あるいは税額控除を認める制度のことをいいます。私立学校や、任意団体などへの寄付は対象となりません。
◆キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書とは、会計期間の収支を資金の取引、性質にしたがって分類して記載したもので、営業活動のみならず資金調達、返済、設備投資等の財務活動を含めた現金の流れを記載します。計算書の表示方法には直接法と間接法があります。証券取引法の適用企業における基本財務諸表の一つとして位置づけられています。企業または企業集団の一会計期間におけるキャッシュ現金・現金同等物の収支を報告する資料。
◆給与所得控除
給与所得控除とは、所得税の給与所得を算定する際に給与収入金額から必要経費に変わる額として差し引くことができるもので、給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いたものとなります。 給与所得控除の金額は、以下の通り計算されます。
給与等の収入総額:給与所得控除額
- ~180万円:収入金額×40%と65万円の高い方
- 180~360万円:収入金額×30%+18万円
- 360~660万円:収入金額×20%+54万円
- 660~1,000万円:収入金額×10%+120万円
- 1,000万円~:収入金額×5%+170万円
◆行政不服審査制度
申告・納税手続きにおいて、税金額の間違いや申告漏れなどがあった場合、税務署が税額等を訂正することを「更正」といい、申告書未提出の場合には、税務署が税額を決める「決定」という処分となります。これら処分に対して不満がある場合、裁判所に提訴することもできますが、手続き費用のかからない方法として、行政不服審査制度があります。
これには、二通りあって、一つは、税務署長に対して処分の3カ月以内に再調査の請求をする方法。これは、認められれば処分取り消しになり、棄却された場合でも審査請求することができます。もう一つが、直接審査請求する方法です。この場合、棄却されると再審査請求か訴訟かを選択肢することになります。
◆金融商品取引法
金融商品取引法とは、証券取引法・金融先物取引法などを整理統合して、多様化する金融取引に対応し、国民経済の健全な発展と投資者の保護や金融商品取引市場の適正な運営、企業の開示制度の整備などを目的とした法律のことをいいます。証券取引法と金融先物取引に関する法律の金融先物取引法を統合したものである。
ひらがな検索